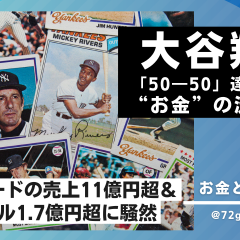インフレ時代の長寿リスクに備える──“減らない資産”をつくる不動産戦略
人生100年時代が現実となった今、問われるのは「寿命」そのものだけでなく、それを支える“資産寿命”の存在です。健康寿命や生活寿命と同様に、資産もまた長く安定して機能することが求められます。特にインフレや社会保障負担が重くなる中、現預金に頼るだけでは生活の安定は維持できません。
本コラムでは、日本人の寿命の変遷とともに、“資産を長持ちさせるための視点”として、不動産をはじめとした投資対象の選び方を、将来の安心につながる観点から解説していきます。
日本人の平均寿命について
人生100年時代と言われて久しいですが、そもそも日本には100歳以上の人はいったい何人いるのでしょうか。総務省のデータを見てみると、2024年9月現在でなんと9万5,119人、そのうち女性が8万3958人で88%を占めています。
過去の日本における寿命の歴史をたどってみると、縄文時代は15歳前後とも言われており、江戸時代で30歳台、明治~昭和の初期で40歳台、昭和55年で73歳、現在は男性で81歳、女性で87歳となっています。
ではなぜ時代とともに人間の寿命が伸びてきたのかと言うと、様々な理由があると思いますが一つには栄養を始めとする食生活の進化、二つ目には医療の進化、ほか様々な要因が重なってきたと考えられます。
ちなみに県別男女別の平均寿命の第一位は下記のようになっています。
都道府県別 平均寿命ランキング
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 1位 | 滋賀県 | 岡山県 |
| 2位 | 長野県 | 滋賀県 |
| 3位 | 奈良県 | 京都部 |
日本人は古来からお祝い事を大切にしてきました。
長寿に関していえば60歳で還暦、70歳で古希、77歳で喜寿、80歳で傘寿、88歳で米寿、100歳で百寿となっています。先ほど述べたように百寿を迎えた方が東京ドーム満席の約2倍もいらっしゃる訳です。
以前、筆者の親戚で100歳を迎えたおじいちゃんがいましたが、当時の青島東京都知事からお祝いのメッセージと品物を受け取ったと聞いています。
この世のあらゆる生物のみならず、太陽や地球そのものにも寿命があるようで、環境問題などに高い意識を持つ事も改めて大切であると考えます。
健康寿命について
(1)健康寿命の長い都道府県は?
寿命はもちろん大切ですが、「健康寿命」もとても大切なキーワードとなります。
健康寿命とは健康で日常生活が制限されずに暮らせる期間と定義されています。厚生労働省が2024年12月に発表した「健康寿命の令和4年値について」によると男性で72.57歳、女性で75.45歳となっているようです。
ちなみに健康寿命の長い都道府県の上位は以下のようになっています。
都道府県別 健康寿命ランキング
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 静岡県 |
| 2位 | 石川県 | 山口県 |
| 3位 | 山梨県 | 岐阜県 |
表にあるように静岡県が男女とも全国で1位となっています。この要因は定かではありませんが、過ごしやすい気候や地元の名産であるお茶を多く飲む、さらに高齢者における労働率の高さなど様々な要因があると考えられます。
(2)健康寿命を保つためには
健康寿命を保つために多くの高齢者の方々が民間や公的部門が運営するスポーツジムや運動施設を利用したり、マスコミが供給する多くの健康番組(健康食)なども含め国民全体に占める健康意識が高まっている事も大きな要因と考えられます。
また今回の参議院選挙においても争点の一つになっているように近年では医療費を含めた社会保険料の負担率がかなり上昇傾向となっています。
つまり病気になる事により、生活費に占める医療費負担が高まる事への警戒感も健康に対する意識を底上げする要因の一つになっているのではないかと考えます。
また健康という側面から考えると肉体的健康のみならず、心の健康も重要視されます。
よく聞く話しですが、定年退職した途端に社会との関係性が希薄となり、孤独感を感じる方も多いと聞いています。先ほど静岡県の健康寿命の理由について述べましたが、日ごろからお茶会を通じておしゃべりをする機会が多いのもその要因の一つではないでしょうか。何らかの形で社会とつながり接点を持つ事により、情報交換や刺激を受けながら心身ともに健康を維持する事が大切であると考えます。
生活寿命について
最近巷でよく話題となるのが、生活寿命です。
あるシンクタンクが発表したデータによると、人間の日常生活の場面における行動パターンは一生涯続くものと一定の年齢を迎えた段階で一気に行動が減るという物です。
筆者が面白いと感じたものは、例えば大盛のラーメンなど何杯もお代わりできる「大盛寿命」や、一晩中寝ないで勉強や物ごとに没頭できる「徹夜寿命」などです。生活寿命は自分自身で気が付かない内にいつの間にか終わっている例がたくさんある訳です。もちろん生活寿命は人によってその差は激しく、その人の生きざまや考え方、興味関心によって左右される事は言うまでもありません。
また生活寿命も人によって異なります。みなさんそれぞれの生活寿命を考えてみるのも面白いかもしれません。
資産寿命について
(1)家計の金融資産とインフレ
4番目に大切なのはいわゆる資産寿命です。
資産には金融資産、証券資産、金の資産、不動産の資産など様々な資産が存在します。現在金融庁の下記のデータを見るとわかる通り、日本には2200兆円近い金融資産が存在しその半分以上は現金・預金となっています。この多くはシニア世帯が保有し、お金が眠っている状態とも言えます。
家計の金融資産
| 残高 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 金融資産合計 | 2,195兆円 | 100% |
| 現金・預金 | 1,120兆円 | 51.0% |
| 債務証券 | 32兆円 | 1.4% |
| 投資信託 | 131兆円 | 6.0% |
| 株式等 | 268兆円 | 12.2% |
| 保険・年金・定形保証 | 571兆円 | 26.0 |
| その他 | 74兆円 | 3.4% |
消費者物価指数が6ヵ月連続で対前年比3%以上も上昇(2025年5月現在)していますが、100万円を金融機関に仮に利息1%で預けてもその間に物価が2%上昇すれば100万円の価値は1%低下する事を意味します。金融資産においてはその時々の経済状況の影響が極めて大きく、端的に言うと、デフレ時代が長期に及べば現金の価値は上昇しますが、逆にインフレが長期に及べば及ぶ程金融資産の価値は低下していく訳です。
(2)資産価値が他力で上昇する資産とは
次に考えたいテーマが自力と他力です。
長期で資産価値が維持でき、上昇していく対象になるための条件の一つが他力です。
例えば同じ不動産投資でも自分が購入した不動産の地域には民間企業や公的部門の投資がまったくないエリア、一方では国土交通省や大手財閥系、ファンド、等が資金を注入し投入するエリアは自分自身が何もしなくても勝手に自分自身の所有する不動産の価値を押し上げてくれる訳です。
2013年のアベノミクス以降、都市再生緊急整備地域、国家戦略特区など様々な再開発の恩恵を受けて資産価値を高めてきた不動産の事例は多くあります。
また不動産以外でも金なども長期に渡って上昇トレンドになっていますが、これは世界で起こっている紛争や有事など様々な不安要素により金の需要が伸びている訳です。
もう一つ金の価値が上昇し続けている大きな理由の一つに金の採掘には有限性があるという事です。つまり価値ある有限なものは時代がどんなに変化しても一定の資産価値を維持できる可能性があるという事です、
(3)GPIFの投資は資産寿命も重要視されている
読者の皆様はGPIFをご存じでしょうか。GPIFとは皆さんが払ってらっしゃる厚生年金などの公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(ちょっと長いですが)です。昨年2024年度は運用利益が何と1兆7,000億円のプラスとなったようです。
年金は次世代も含めた長期の運用が重要ですので、年金財政の安定化へGPIFは多くの投資対象に長期に渡り運用を施しています。
実はこのGPIFの中にはリートも含まれており、リートの中にはオフィス、商業施設、物流施設、の他、マンションなどの住宅系も含まれています。まさに長期安定を目指す資産運用の中に不動産が重要な役割を果たしている事が分かります。
(4)資産寿命の長い資産とは
人生100年時代を迎え、はやり経済的な自立、所有する資産は歳を取ればとるほど、その重要性は増してきます。決して贅沢な暮らしをするためにではなく、普通の生活ができ、時には自分や回りの人に対するプチご褒美や趣味や楽しみに費やせる一定の資産がある事が大切です。
では資産寿命が長い投資対象になるためにはどのような条件が必要でしょうか。筆者が考える条件として長期に渡って需要があるものに投資をしていく事が大切であると考えます。
ここで読者の皆様にクイズを出します。
<クイズ>:
不動産投資をする場合、Aマンションは面積が70㎡、80㎡と広く間取りも3LDK、4LDKと比較的面積の広いマンション、そして駅からバス便などやや駅から遠いマンション。Bマンションはワンルームやコンパクトマンションなど比較的面積が広くはなく、しかし都心までの距離や、駅までの距離が比較的短いマンション。どちらが長期的に安定した需要が見込まれるでしょうか。
答えは、筆者が考えるには今後20年30年という長期の人口動態予想(厚生労働省データ)などを見ても圧倒的に単身者向けの需要が長期に渡って続く事が想定されますのでBマンションとなります。
購入需要や賃貸需要がある不動産はそれだけ需要があるからこそ資産価値が維持できる訳です。需要が低下する不動産は結果的には空室となり資産価値も低下します。
近年問題となっていますが、管理不全マンションなども資産寿命を短くする傾向にあります。また労働人口が減少するエリアも資産価値が下がりやすい傾向になります。
以上述べてきたように様々な寿命がありますが、一つひとつ全て極めて大切なものです。皆様の参考にして頂ければ幸いです。今年は特に厳しい猛暑となっておりますので、まずは健康と健康寿命に注意を払いたいものです。