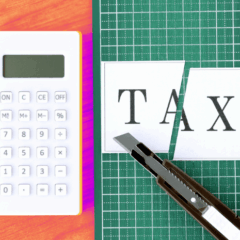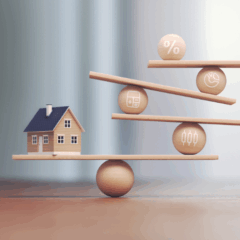外国人労働者の増加が不動産投資に与える影響【230万人突破】人口減少下の賃貸市場で勝つ戦略
日本の人口減少と少子高齢化は、もはや避けられない構造的な課題です。生産年齢人口が6割を割り込む中、日本の労働力を支える外国人労働者数は230万人を突破し、過去最高を更新しています。このダイナミックな変化は、単なる社会現象ではありません。特に三大都市圏における住宅・賃貸市場に劇的な影響を与えており、この変化は日本の不動産投資市場にも直結する重大な影響をもたらしています。
本コラムでは、最新の就業動向や在留外国人数、政府の政策動向をデータで検証し、外国人労働者の増加が不動産投資市場に具体的にどのような影響をもたらすかを解説します。ワンルームマンション市場の将来性を含め、日本の構造変化を投資機会に変えるための視点を提供します。
日本経済と構造的な労働力人口の減少
日本の人口は2008年でピークを迎え、以降減少傾向が続いています。さらに高齢化の進行から若い世代の人口が減少し、労働力人口の減少も社会的な課題となっています。
2005年には総人口における生産年齢人口(15~64歳人口)は8442万人で66.1%でしたが、少子高齢化から生産年齢人口が減少していき、2024年には生産年齢人口は7372万人となり60%を割り込み、2025年9月1日現在(概算値)では7348万人で59.7%となっています。
日本の人口推計 2025年9月1日現在(概算値)
| 総数 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 1億2317万人 | 1350万人 | 7348万人 | 3619万人 |
| 割合 | - | 11.0% | 59.7% | 29.4% |
一昔前までは、過酷な労働環境を現わすいわゆる「3K」業種が敬遠されて人手不足が問題となりましたが、現在では全体的な就業人口が減少するという構造的な問題に直面しています。この労働力不足を補う主要な手段こそ、外国人材の活用であり、これが結果的に日本の賃貸市場の構造変化を促しています。
データで見る外国人就業・在留外国人の増加
外国人労働者数の急増とその内訳
日本では外国人労働者の数が急速に増加しています。厚生労働省の発表によると2024年10月時点での外国人労働者数は約230万人で、前年比12.4%の増加でした。特に大都市圏への集中が顕著です。
| 都市別(上位3位) | 労働者数(概数) | 占める割合 |
| 東京都 | 約58万人 | 25.4% |
| 愛知県 | 約22万人 | 10.0% |
| 大阪府 | 約17万人 | 7.6% |
業種別では「製造業」が最も多く、次いで「サービス業」、「卸売業・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「建設業」などが続きます。東京ではサービス・飲食業の割合も多く、生活に密着した分野での外国人労働者の存在感が増しています。
在留外国人数と出生数の増加
働く外国人が増えることで、当然、日本に住む外国人の数も増加しています。在留外国人数は2024年末には約376万人に達し、前年比で10.5%の増加です。
特に東京都では、2024年の人口増加の約8割が外国人によるものであり、外国人 住宅需要 東京圏での高まりを裏付けています。また、外国人出生数も2024年には2万人を超え、日本人出生数の減少を部分的に補う形となっており、今後も安定的な居住者層として増加が見込まれます。
出典:出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」および厚生労働省「人口動態統計」
外国人増加が不動産投資市場にもたらす影響
日本における外国人人口の増加は、もはや一過性のトレンドではなく、日本の賃貸市場の構造変化を決定づける要因となっています。この変化は、不動産投資家にとって大きな機会を意味します。
賃貸需要の底上げとエリア集中
今後ますます外国人労働者が増加していくことで、当然ながら国内の住宅需要は増加します。特に、製造業、サービス業、IT産業が集積する三大都市圏(東京、愛知、大阪)では、賃貸住宅の需要が底上げされます。
- 社宅需要の増加: 外国人を受け入れる企業は、安定的な労働力確保のため、社宅や共同住宅として賃貸物件を一括で借り上げるケースが増加しています。
- 単身者・留学生の増加: 高度人材や留学生の流入増加により、利便性の高い都心や主要大学周辺での単身者向け物件(ワンルームマンション 外国人需要)が高まっています。
- 地方での大規模開発: 北海道倶知安町での大規模な外国人労働者向け共同住宅の建設許可のように、地方でも特定の産業(観光、農業など)を背景にした需要が生まれています。
投資対象としてのワンルームマンションの将来性
こうした外国人労働者の増加傾向は、都心近郊のワンルームマンション市場にとって特に有望です。
- ターゲット層の明確化: 外国人単身者、または企業による社宅・寮としてのニーズは、単身者向けのコンパクトな住居に集中しやすいため、投資対象が明確になります。
- 利便性の重視: 交通アクセスや生活利便性を重視する傾向が強いため、駅近や都心部の物件は高い入居率を維持しやすいと考えられます。
- 高い入居率の維持: 生産年齢人口の減少によって日本人単身者が減っても、外国人労働者という新たな層が需要を補填するため、空室リスクの軽減につながります。
マネーの流入と投資機会の拡大
外国人労働者 不動産投資 影響は賃貸需要だけではありません。海外からの優秀な人材の誘致に加え、東京を中心に海外マネーの流入も加速しています。外資系企業の誘致(アジアヘッドクォーター特区など)や、モルガン・スタンレーのような大手投資会社が日本に特化した不動産ファンドを投入するなど、グローバルな投資マネーが日本の不動産に注目しています。
さらに、不動産会社でも外国人向けの営業マンが増え、「売る人・買う人・借りる人」が全て外国人という取引も増加しており、市場の国際化が急速に進んでいます。
まとめ:構造変化を投資機会に変えるために
今後ますます日本人の労働人口が減少し、外国人が大きく増加していくと予想されます。日本に住む外国人が増加する事で、当然の事ながら住宅需要も増加して行きます。2025年10月には北海道では外国人労働者・外国人観光客共に多い倶知安町(くっちゃんちょう)で、外国人労働者向けの共同住宅を農地に建設する計画が許可された報道がありました。居住者は街の人口の1割にあたる1,200人と大規模な住宅です。
政府は国家戦略特区や東京都のアジアヘッドクォーター特区など、再開発により外資系企業の誘致にも力を入れており、東京の国際化が進む中でますます外国人労働者の役割も大きくなっていきます。海外から優秀な人材を誘致すると共に外資など東京を中心に資金の流入が増えています。例えばモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが日本に特化した不動産ファンドを投入するそうです。東京にはこれまで述べたように海外からの人材の流入だけではなくマネーの流入も加速してきています。
不動産投資業界においては、外国人の賃貸需要が増加しているだけでなく、投資としてマンションを購入する外国人も増えています。これに対応して各不動産会社でも外国人の営業マンを増やしており、「売る人・買う人・借りる人」が全て外国人という状況も珍しくはなくなってきています。
外国人労働者の多い大都市圏では、今後ますます外国人の住宅需要が高まってきます。特に単身者の外国人の方、また外国人を受け入れる企業の社宅としての役割も果たすワンルームマンションは、今後も有望な市場と言えます。
野中 清志(のなか きよし)
住宅コンサルタント
マンションデベロッパーを経て、2003年に株式会社オフィス野中を設立。
首都圏・関西および全国でマンション購入に関する講演多数。内容は居住用から資産運用向けセミナーなど、年間100本近く講演。