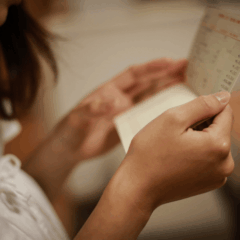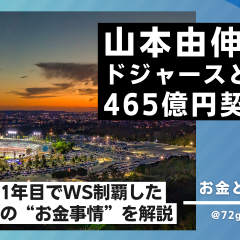【2025年基準地価】全国平均1.5%上昇。東京・北海道で二極化進む不動産市場の今
国土交通省が発表した2025年の基準地価は、全国平均で前年比+1.5%と、1991年以来の高水準を記録しました。上昇をけん引したのは、再開発とインバウンド需要が重なる東京都心部、そして「第二のニセコ」と呼ばれる北海道エリア。
不動産価格が再び上昇局面を迎える中、投資家にとってどの地域がチャンスとなるのか──。地価の動向から見える「資産価値の再評価ポイント」を読み解きます。
全国の地価は
国土交通省が2025年9月16日に発表した基準地価(都道府県地価調査)によると、全国の住宅地・商業地を含む地価は全用途平均で前年比1.5%の上昇となりました。4年連続の上昇で、1991年に3.1%の上昇となって以来の高い上昇率となりました。
圏域別に見ると、東京圏では住宅地で3.9%、商業地で8.7%、工業地で6.7%とそれぞれ高い上昇率となりました。大阪圏、名古屋圏などでも地価上昇率が拡大しています。
また地方圏でも上昇が続いています。
新型コロナの発生から調整局面にあった地価は、再び新型コロナ発生前の水準に回帰する動きが強まってきています。株価の上昇、インバウンドの増加などで日本経済も力強く回復しており、今後も地価上昇が続く可能性もあります。
2025年基準地価:圏域別 対前年地価変動率の推移
| 住宅地 | 商業地 | 工業地 | ||||
| 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | |
| 東京圏 | 3.6% | 3.9% | 7.0% | 8.7% | 6.6% | 6.7% |
| 大阪圏 | 1.7% | 2.2% | 6.0% | 6.4% | 6.3% | 6.8% |
| 名古屋圏 | 2.5% | 1.7% | 3.8% | 2.8% | 3.5% | 2.5% |
| 三大都市圏 | 3.0% | 3.2% | 6.2% | 7.2% | 6.0% | 6.1% |
| 地方圏 | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 1.0% | 2.4% | 2.4% |
全国の地価上昇率ランキング
全国で地価上昇率が高かった上位5地点を見てみましょう。
住宅地では北海道の富良野市の地点が上昇率27.1%で1位となりました。富良野と言えば昔の人気ドラマで一躍有名になった所です。観光地として外国人にも人気があり、またスキーも楽しめるので「第二のニセコ」として注目を集めています。
2位と3位は「ラピダス」の進出で注目を集めた千歳市の地点で、地価上昇率は23%台となりました。この背景には企業の進出により大幅に雇用が増え住宅の需要が押し上げられた事が要因と考えられます。
4位も北海道で真狩(まっかり)の地点が19.7%となりました。ニセコや俱知安、羊蹄山や洞爺湖などの近くに位置しリゾート需要が多く見込めるエリアです。歌手の細川たかしさんの出身地としても知られています。
また外国人に人気の「ニセコ」、そして「エスコンフィールドHOKKAIDO」の開業により北広島市などのエリアで地価が上昇してきました。北海道はアジアの中のリゾート地として今後も各地で地価が上昇する可能もあるのではないでしょうか。
5位は茨城県つくば市の地点で19.6%の上昇です。環境が良く東京へも比較的近い割に価格も高くなく、また子育てもしやすく待機児童数0人を達成しており、人口増加率も高いエリアです。地価が大きく上昇した背景には東京都区内の住宅価格の上昇により比較的手が届きやすいエリアの需要が地価を押し上げた事があります。
2025年基準地価:上昇率順位表(全国)<住宅地>
| 順位 | 都道府県 | 所在地 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 富良野市北の峰町1981番62『北の峰町11-21』 | 27.1% |
| 2 | 北海道 | 千歳市東雲町5丁目52番 | 23.2% |
| 3 | 北海道 | 千歳市栄町5丁目3番外内 | 23.1% |
| 4 | 北海道 | 虻田郡真狩村字真狩44番17 | 19.7% |
| 5 | 茨城県 | つくば市みどりの東39番9 | 19.6% |
商業地もやはり北海道が多く、3位までを千歳市の地点が占めました。4位は長野県の安曇野、5位は岐阜県の高山市など観光地として有名なエリアの地価上昇率が高くなっています。高山市は飛騨高山など江戸時代の名残のある街並みが有名です。インバウンドの増加もあり、商業地でもこうした観光地の地価が大きく上昇しています。
2025年基準地価:上昇率順位表(全国)<商業地>
| 順位 | 都道府県 | 所在地 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 千歳市末広2丁目122番2外内『末広2-6-3』 | 31.4% |
| 2 | 北海道 | 千歳市北栄2丁目1345番27『北栄2-3-9』 | 29.9% |
| 3 | 北海道 | 千歳市東雲町1丁目6番4 | 29.6% |
| 4 | 長野県 | 北安曇郡白馬村大字北城字新田3020番837外 | 29.3% |
| 5 | 岐阜県 | 高山市上三之町51番 | 28.1% |
東京都の地価動向
東京都の地価動向について見てみましょう。
住宅地では東京都全体で5.7%、都区部で8.3%の上昇となり、特に都心部では12.7%と平均で高い上昇率となりました。
商業地では東京都全体で11.4%、都区部で13.2%と高い上昇率となり、さらに都心部では平均では15.3%と大きく上昇しました。
東京への企業など経済の一極集中により人口流入が全国でも最も多く、さらに再開発の進行、新線計画などで東京の利便性が増し、地価も大きく上昇している事が分かります。
東京都の地域別対前年平均変動率
| 住宅地 | 商業地 | |||
| 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | |
| 東京都 | 4.7% | 5.7% | 8.5% | 11.4% |
| 東京都区部 | 6.7% | 8.3% | 9.7% | 13.2% |
| 区部都心部 | 9.2% | 12.7% | 11.0% | 15.3% |
| 多摩地域 | 3.0% | 3.5% | 4.5% | 5.4% |
区部都心部:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区
都区部の区別の地価上昇率
東京都の地価を区別に見ると、住宅地では港区と目黒区が13.7%と最も地価が上昇しました。3位は台東区、4位は中央区となりました。都心三区のうち港区や中央区などの地価が上昇し、さらに地価上昇がその周辺となる目黒区、台東区、品川区などのエリアに波及しています。東京都区部平均では8.3%の上昇となりましたが10%以上の上昇となった区は12区もあります。
商業地では最も地価上昇率が大きかったのは浅草などの観光地のある台東区で、平均で18.2%と非常に高い上昇率となりました。以下、中央区、文京区、千代田区などが続きました。
杉並区が5位にランキングました。中央線沿線や丸ノ内線を始め多くの路線が利用できる交通利便性や生活利便性から元々住宅地としても高い人気があり、都心5区の住宅価格高騰により都心の住宅を諦めた方が杉並区の住宅需要を押し上げたと考えられます。
東京23区の商業地のうち18の区が10%以上の上昇となりました。投資用のワンルームマンションなどは商業地に建設される事が多いので、今後もさらにマンション価格・賃料の上昇などに拍車をかける可能性もあります。
2025年基準地価 区別対前年地価上昇率ランキング(住宅地)
| 順位 | 区 | 変動率(%) |
|---|---|---|
| 東京都区部 | 8.3% | |
| 1 | 港区 | 13.7% |
| 1 | 目黒区 | 13.7% |
| 3 | 台東区 | 13.4% |
| 4 | 中央区 | 13.3% |
| 5 | 品川区 | 12.9% |
2025年基準地価 区別対前年地価上昇率ランキング(商業地)
| 順位 | 区 | 変動率(%) |
|---|---|---|
| 東京都区部 | 13.2% | |
| 1 | 台東区 | 18.2% |
| 2 | 中央区 | 16.7% |
| 3 | 文京区 | 16.4% |
| 4 | 千代田区 | 16.2% |
| 5 | 杉並区 | 16.1% |
東京都の地価上昇率ランキング
東京都で最も地価上昇率が高かったのは、住宅地では新宿区の「市谷船河原町(いちがやふながわらまち)」の地点でした。中央線のある外堀に面したエリアで、飯田橋と市ケ谷、牛込神楽坂など駅の間に位置します。この周辺は新宿区を代表する高級住宅街で、かつて筆者が在籍していた大京初の億ション「ライオンズマンション市ケ谷砂土原」が分譲されたエリアにも近い場所です。
2位は神宮前3丁目の地点で、表参道から奥に入った住宅地です。都会の喧騒から離れた静かな住宅地ですが、表参道ヒルズや開発の計画されている神宮外苑などにも近い立地です。3位は赤坂1丁目の地点です。溜池山王、六本木、神谷町、虎ノ門ヒルズ等の駅が全て10分以内であり、アークヒルズや開発の進む虎ノ門のビジネス街などが全て徒歩圏の好立地にあります。公共の開発が地価を押し上げた例とも言えます。
4位の猿楽町は超人気エリアである「代官山」駅にも近く「ブランド力」は年数が経過しても劣化しない事を示しています。
5位の北品川5丁目は2013年に三井不動産レジデンシャルが「パークシティ大崎 ザ・タワー(品川区北品川5丁目)」を分譲した際に同社のコラムを執筆しました。当時も基準地価の上昇率が住宅地で1位となっていました。あれから12年、現在においても高い上昇率を示している事からも人気の高さが窺えます。
2025年基準地価 基準地上昇率ランキング(東京都・住宅地)
| 順位 | 区 | 基準地の所在「住居表示」 | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 市谷船河原町19番8外 | 15.9% |
| 2 | 渋谷 | 神宮前三丁目13番13「神宮前3-13-13」 | 15.7% |
| 3 | 港 | 赤坂一丁目1424番1 「赤坂1-14-11」 | 15.6% |
| 4 | 渋谷 | 猿楽町18番29 「猿楽町15-3」 | 15.6% |
| 5 | 品川 | 北品川五丁目628番2外 「北品川5-9-28」 | 15.4% |
| 5 | 豊島 | 高田三丁目770番1 「高田3-32-7」 | 15.4% |
商業地では台東区の浅草1丁目が27.4%の上昇で1位、2位が西浅草2丁目で25.2%の上昇です。インバウンドの大幅な増加によりこうした観光地の地価が大きく上昇しています。3位は中央区の湊1丁目で八丁堀駅の東側に位置します。茅場町や東京、銀座などにもアクセスしやすい地点です。中央区ではホテルやマンションの建設が増加し地価上昇が進んでいると考えられます。
2025年基準地価 基準地上昇率ランキング(東京都・商業地)
| 順位 | 基準地の所在地 『 』は住居表示 | 変動率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 台東区 | 浅草一丁目17番9『浅草1-29-6』 | 27.4% |
| 2 | 台東区 | 西浅草二丁目66番2『西浅草2-13-10』 | 25.2% |
| 3 | 中央区 | 湊一丁目16番2『湊1-2-7』 | 25.0% |
| 3 | 渋谷区 | 円山町86番2外『円山町22-16』 | 25.0% |
| 5 | 中央区 | 銀座七丁目205番14『銀座7-16-7』 | 24.9% |
東京都の価格高順位ランキング
東京都で最も土地の価格が高かったのは、住宅地では「港区赤坂一丁目」の地点で1㎡あたり643万円となりました。この地点は先ほども述べましたが地価上昇率は住宅地で3位となりました。
上昇率2位以降は千代田区の「番町」や「麹町」などがランキングしています。「番町」とは江戸時代に江戸城の警備のための旗本が住んでいた事が地名の由来です。番町は旧江戸城の外堀の内側にあり、千鳥ヶ淵に面したエリアで、億ションの発売されるエリアとしても有名です。「麹町」も番町の近くに位置します。
こうした歴史のある高級住宅街はブランド性とともに地価が高く維持されています。
また千代田区は投機的なマンションの購入について抑制するように不動産団体に要請をしているという事もあるほど都心部の地価・マンション価格が大きく上昇しています。
ちなみに東京都の住宅地価格上位10位のランキングはそのまま全国の上位10位となります。
2025年基準地価 東京都 基準地価格高順位ランキング(住宅地)
| 順位 | 区 | 基準地の所在地 『 』は住居表示 | 2024年円/㎡ | 2025年円/㎡ | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港 | 赤坂一丁目1424番1 「赤坂1-14-11」 | 5,560,000 | 6,430,000 | 15.6 |
| 2 | 千代田 | 六番町6番1外 | 4,620,000 | 5,100,000 | 10.4 |
| 3 | 千代田 | 三番町9番4 | 3,580,000 | 4,050,000 | 13.1 |
| 4 | 千代田 | 麹町二丁目10番4外 | 2,990,000 | 3,290,000 | 10.0 |
| 5 | 千代田 | 二番町12番10 | 2,650,000 | 3,010,000 | 13.6 |
商業地で最も地価が高かったのは中央区銀座2丁目の「明治屋銀座ビル」の地点で1㎡あたり4,690万円となりました。2位も銀座で6丁目の「GINZA SIX」などが近い地点です。銀座は高級店が建ち並ぶブランドエリアとして知られており、また最近ではインバウンドも多く訪れますので、地価や不動産価格なども高い水準が維持されています。
3位は港区北青山3丁目の地点です。「北青山三丁目地区市街地再開発事業」が2025年に着工し大規模な再開発が進められています。表参道などのブランドエリアや、今後大きな開発の予定されている神宮外苑なども近いエリアです。
4位と5位はどちらも東京駅前のビジネス街である丸ノ内と大手町となりました。
東京都の商業地価格上位5位まではそのまま全国上位5位と同じとなります。
2025年基準地価 東京都 基準地価格高順位ランキング(商業地)
| 順位 | 区 | 基準地の所在地『 』は住居表示 | 2024年円/㎡ | 2025年円/㎡ | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央 | 銀座二丁目2番19外「銀座2-6-7」 | 42,100,000 | 46,900,000 | 11.4 |
| 2 | 中央 | 銀座六丁目4番13外「銀座6-8-3」 | 30,000,000 | 33,000,000 | 10.0 |
| 3 | 港 | 北青山三丁目33番2 | 29,000,000 | 30,600,000 | 5.5 |
| 4 | 千代田 | 丸の内三丁目2番外 「丸の内3-3-1」 | 27,000,000 | 27,300,000 | 1.1 |
| 5 | 千代田 | 大手町一丁目5番39外 「大手町1-8-1」 | 25,700,000 | 26,000,000 | 1.2 |
国土面積に比べて世界的にも極めて高い経済力を有する日本の土地は、とても希少性が高いと言えます。特に外資も含めた民間投資・公共投資などが地価を押し上げる要因ともなっています。
昨今では金価格も1グラム2万円を超すなど高騰しています。駅に近い土地やブランドエリアの土地と金の共通点とは何でしょうか?それはズバリ、有限性がある事です。
今後の皆様の住宅購入・不動産投資における参考材料にして頂ければ幸いです。
野中 清志(のなか きよし)
住宅コンサルタント
マンションデベロッパーを経て、2003年に株式会社オフィス野中を設立。
首都圏・関西および全国でマンション購入に関する講演多数。内容は居住用から資産運用向けセミナーなど、年間100本近く講演。